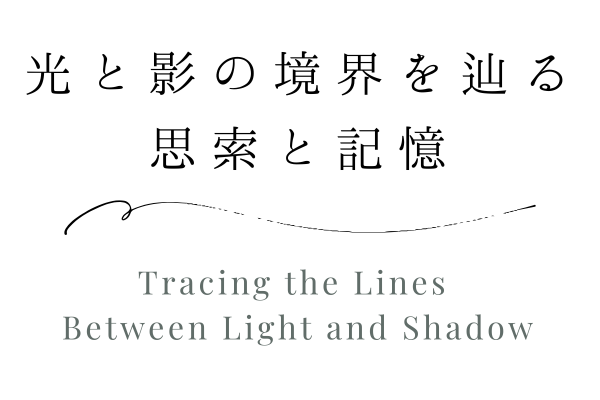あの夜のオリオン座を見上げていると、以前読んだ「オリオン座を天宇受売命に見立てる考察」を思い出した。神話の解説だけでなく、星座図と天宇受売命の姿を重ねた図まで作っられていて、かなりクリエイティブなのに、妙に説得力があった。 (天宇受売命とオリオン座)
まず、天宇受売命と天岩戸の神話。
天照大神が天岩戸に隠れて世界が闇に沈んだとき、神々の前で天宇受売命が踊る。場が大笑いに包まれ、その気配に誘われるように天照大神が岩戸を少し開け、光が戻る――あの話だ。
ここで大事なのは、天宇受売命の踊りが「上品な舞」ではないところだと思う。『古事記』には、神がかりになって胸乳をあらわにし、裳緒をホト(陰部)に押し垂らした、という趣旨の記述がある。つまり、場を揺らすための踏み込みが最初から組み込まれている。
闇を力でこじ開けるのではなく、笑いで空気をひっくり返して、「出てきたくなる流れ」を作る。私はこの感じが好きだ。
そして、その考察が面白いのは、オリオン座の各部位を「踊る天宇受売命の身体」に見立てていくところだ。たとえば、右手にかざした棍棒は、天宇受売命がさしかざした小竹葉に。ベルトの三連星は帯に。さらに、オリオン大星雲(M42)とその周辺は、神話の表現と重なる身体の「象徴」として読まれていく。さらに踏み込むと、肩の赤いベテルギウスが身体のアクセントになり、裳の白さに見立てられる星も出てくる。ちょっと大胆で、だからこそ場が沸く感じがある。全部を説明しきれないけれど、図で見ると「そう見える」ところまで連れていかれる。 (天宇受売命とオリオン座)
こういうのって、正解を当てる話じゃない。
でも、あの夜の私には、すごく腑に落ちた。
というのも、オリオン座は、そもそも日本でもいろいろな呼ばれ方をしてきた星座だ。鼓(つづみ)に似ているから「鼓星」と呼ばれたり、ベテルギウスとリゲルの色の対比が「平家星」「源氏星」と結びついたりする。つまり、昔から私たちはオリオン座を見立てで受け取ってきた。 (ホンダ)
そして、あの見立ての話。
ある研究者は、天孫降臨神話の猿田毘古神を牡牛座のヒアデス星団に、向かい合う天宇受売命をオリオン座に、天の八衢を昴(プレアデス)に相当すると見る、と紹介されている。(勝俣氏の日本神話の解釈)
オリオン座の近くに牡牛座や昴が並ぶ冬の空を思うと、たしかに「向かい合う配置」として、身体感覚には落ちてくる。
私の写真では、赤く静かなベテルギウスが左下に、青白いリゲルが右上に写っている。時間や向きで星座は回転して見えるのに、あの二つの光の「性質の違い」だけは変わらない。
包むような赤と、背中を押すような青白さ。
強さと静けさが、同じ輪郭の中で共存している。
天宇受売命の踊りも、きっと同じだ。
大胆さと繊細さ。はみ出しと、祈り。
どっちかだけでは岩戸の奥の心は動かない。両方が同居して、場が揺れる。
だから私は、あの考察を「当たってる/当たってない」より先に、ひとつの芸術として好きになった。
あのブログで表現されているように、冬の夜空で踊る古代の美女という見立ては、ヒゲもじゃの狩人より、たしかに美しい。
そして何より、私の中の「閉じたい」と「出たい」を、同じ空に同居させてくれた気がした。
次は、写真に写ったベテルギウスとリゲル――あの赤と青の対比を、もう少しだけ言葉にしてみたい。
あの夜、私の中で落ち着いたものの正体は、たぶんそこにある。

シリウスとプロキオンもいて冬の大三角も
前の記事:あの夜のオリオン座(1)
次の記事:あの夜のオリオン座(3)〜 赤と青のあいだ(完)