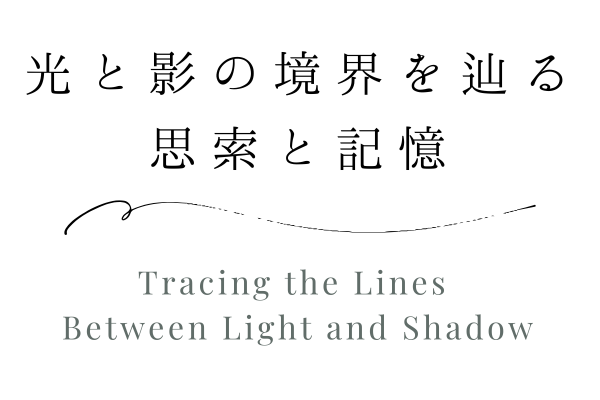ずっと、ベートーヴェンが苦手だった。彼の曲が流れ出すと、頭の中にパッと「四角い形」が浮かんでしまう。(共感覚1の一種?)それは角があって、きちんとしすぎた箱が整然と並んでいるイメージ。「1ミリのズレも許されない。もし整列が乱れたら、先生に怒られてしまう……」そんな窮屈さが、どこかにある。もちろん、それが誰にも真似できない見事で美しい名曲たちだということは分かっている。けれど、聴いている間中、どこか背筋を伸ばして、いい子にしていないといけないような気がして、なんというか、ちょっと息苦しい感覚を覚えてしまうのだ。
そんな私が、唯一、不思議と息苦しくならなかったのが交響曲第7番の第2楽章だった。(ページの終りに音源あり)理由は最初は全くわからなかった。あの曲には、なぜか例の「四角い窮屈さ」がない。終わりのない円環のような印象で、淡々と、タ、タタ、タ、タと呪文のように繰り返されるリズムに身を委ねていると、むしろ肩の力が抜けていく。現代のミニマル音楽2やポストクラシカル3で頻繁に聴かれる反復のように、これがある意味聞き手をトランス状態(没入状態)に誘うのではないか。後に、バシャール4がこの曲を「癒やしをもたらす」と語っているのを知ったときは、驚くと同時に、自分の感覚の正しさを証明されたようで嬉しかった。
あの時感じたのは、意志の力で築かれた「四角い壁」が崩れ、音がただの「揺らぎ」として空間を浸食していく心地よさだった。
その心地よさの正体を突き詰めていくと、私が本当に愛している音楽たちの姿が見えてくる。たとえば、光と色彩が本当に美しい印象派の音楽。インクが水に滲むように境界が消えていくポストクラシカルの音の世界。あるいは、幾層もの旋律がさざなみのように重なり合うルネッサンスのポリフォニー5や、教会の高い天井の空間そのものに共鳴するような聖歌。そして、どこからが始まりで、どこが終わりかも判然としないアンビエント6。
それらの音楽には、境界線がない。誰かに命じられた正解の形などなく、音はただ、そこにある。アルヴォ・ペルト7の静まり返った水面のような響きや、マックス・リヒター8の記憶に滲む弦の音。それらは理屈を超えて、私の細胞を直接震わせる。なぜ、こういう音楽たちに自分が惹かれるのか、具体的に知りたいと思い、音楽理論の解説動画を見て「リディア旋法9」や「倍音10」の仕組みを学ぼうとしても、正直、内容はさっぱりわからなかった(笑)でも私の耳だけは、それが「解放の音」であることを知っている。
ベートーヴェンの晩年の曲、弦楽四重奏曲第15番の第3楽章(記事の終わりに音源あり)を聴くとき、私は確信する。あの完璧主義の巨匠でさえ、最後には「いい子・優等生」でいることをやめ、設計図という境界線を捨てて、この広大な揺らぎの海に飛び込んだのではないか、と。
四角い箱の外には、こんなにも自由で、優しい世界が広がっている。自分の耳が選ぶ「心地よさ」を信じて、私は今日も、境界線の溶け出す響きの中に、深く潜っていく。音楽理論とか理屈なんて、本当はなくてもいいのかもしれない。言葉にできない揺らぎに身を委ね、ただそこにある音と溶け合える瞬間がある。それだけで、この世界に音楽があって本当によかったと、心の底から思うのだ。
私が愛した、四角くないベートーヴェン
交響曲第7番 第2楽章
「いい子」の緊張を解いてくれる、癒やしの反復。バシャールが語り、私の身体が納得した、不思議な共鳴の調べです。
弦楽四重奏曲第15番 第3楽章
巨匠ベートーベンが晩年に四角い整列した設計図を捨てて、天上の「揺らぎ」に身を委ねた瞬間。ノン・ビブラートの澄んだ音が重なる、境界線のない海。
脚注
- 共感覚(Synesthesia) ある一つの刺激に対して、本来の感覚に加えて異なる種類の感覚が自動的に生じる現象。例えば「数字の2が赤く見える(色字)」「ピアノの音が尖った図形に見える(音視)」などがある。病気ではなく、脳内の感覚領域の相互作用によるものと考えられており、芸術家や作家にも多く見られる。 ↩︎
- ミニマル・ミュージック(Minimal Music)1960年代に登場した現代音楽の一種。音の動きを最小限(ミニマル)に抑え、短いパターンを繰り返しながら徐々に変容させることで、聴き手を瞑想的・催眠的な状態へ導く効果がある。 ↩︎
- ポスト・クラシカル(Post-Classical): 2000年代以降に定着したジャンル。クラシックの技法を基盤としながら、アンビエント(環境音楽)や電子的な音響処理を取り入れ、ジャンルの境界を越えた自由な表現が特徴。マックス・リヒターやオーラヴル・アルナルズがその先駆者とされる。 ↩︎
- バシャール(Bashar) ダリル・アンカがチャネリングする、エササニ星という惑星に住む宇宙存在。1980年代から「ワクワクすることに従って生きる」という哲学を提唱し、精神世界の分野で世界的に高い知名度を持つ。 ↩︎
- ルネサンス・ポリフォニー(Renaissance Polyphony):15世紀から16世紀にかけて発達した作曲技法。一つの主旋律に従属するのではなく、それぞれの声部が独立したメロディとして歌われ、それらが複雑に絡み合いながら全体として美しい調和(ハーモニー)を生み出す。「模倣(ある声部が前の声部のメロディを追いかける)」という手法が多用される。 ↩︎
- アンビエント(Ambient Music): 1970年代にブライアン・イーノが提唱した「環境音楽」。聴くことを強制せず、空間の一部として存在することを目的とした音楽ジャンル ↩︎
- アルヴォ・ペルト(Arvo Pärt):エストニアの作曲家。中世・ルネサンスのポリフォニーを長年研究。三和音の響きを基調とした極限までシンプルで美しい独自の作曲技法「ティンティナブリ様式」を生み出した。その音楽は、深い静寂と精神性を湛え、ポスト・クラシカルやミニマル・ミュージックの文脈でも高く評価されている。 ↩︎
- マックス・リヒター(Max Richter):ドイツ出身の作曲家、ピアニスト。ミニマリズムを継承しつつも叙情的で物語性の強い世界観を構築した。ヴィヴァルディの『四季』を再構築した作品や、睡眠中に聴くことを想定した音楽など、音楽の概念を拡張する試みを続けている。 ↩︎
- リディア旋法(Lydian Mode):明るく浮遊感のある響きを持つ古い音階。第4音が半音高く、空想的、あるいは神聖な雰囲気を作り出す。 ↩︎
- 倍音(Overtones / Harmonics):一つの音が鳴るとき、その基礎となる音(基音)と一緒に、その整倍数の周波数で同時に鳴っている高い音のこと ↩︎