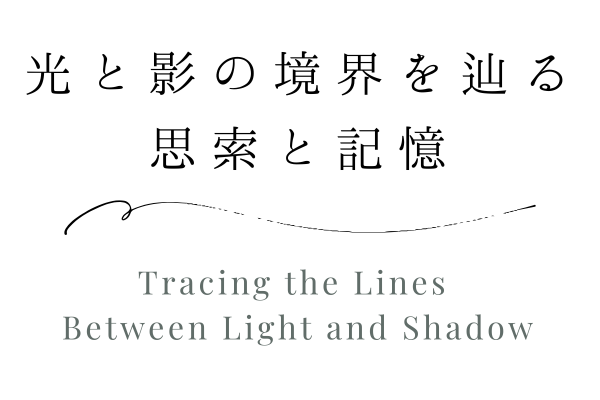今、チェンマイ郊外のチェンダオは、ものすごい熱気に包まれている。 年々規模が大きくなる大イベント「シャンバラ祭り」。自然と調和し、文明から少し距離を置いて自分を取り戻そうとする、日本人が始めた共同創造的かつ自然回帰的な素敵なイベントだが、今や国籍も多様な人々が押し寄せており、かつて私たちが静寂を求めて通った付近の温泉も、今は観光客でごった返している。
「門戸を開く」という意味では素晴らしいことなのだろう。けれど、深く静かに自分を探求したい者にとって、その賑やかさは時に、内側の湖をかき乱す雑音になってしまう。今の私が大切に育みたいのは、もっと微細で、壊れやすい言葉以前の感覚や浮上してきた記憶の産声だ。
それは喧騒に耐えられるか、という修行の問題ではなく、今の自分の聴き取ろうとしている周波数にふさわしい環境を、贅沢に、そして厳格に選ぶという意志。だから私は、迷わずそのノイズを避けることにした。
険しい道のり、その先にある聖域
そんな大規模イベントを横目で見ながら私と瞑想仲間5人が向かったのは、チェンダオからさらに北西へ2時間のウィエンヘーン。 最近、私はこの険しい山道を何度も自分でハンドルを握り、手にも汗を握りつつ断崖の道を越えていく。
恐れが日常に変わり、慣れが確信に変わる。この「運転の集中力」さえも、私にとっては内なる静寂へと向かうための大切なプロセスだ。自分の人生のハンドルを他者に預けず、自らの意志で行きたい場所へ向かう。その実感が、私を「独り内観」の入り口へと運んでくれる。
境界線で見つけた言葉以前の笑い
数回めになるリス族の村での体験はまた後日記録するとして、今回の旅の最終日にたどり着いたのは、タイとミャンマーの両側にまたがるという不思議なお寺、Wat Fa Wiang Inn1だった。 低い土嚢と石ブロック、竹のフェンス。あまりにもシンプルで頼りない「境界」を前に、私たちは誰からともなく「スパイごっこ」を始めた。
後で写真を見て、私たちは大笑いした。 みんな可愛らしく身を潜めているのに、なぜか私のお尻だけが、画面の中で圧倒的な存在感を放っている。 「私のお尻、巨大すぎる!笑」 まさに「超安産でした」と言わんばかりの、生命力にあふれた形。
かつて経験した人生の強制リセット。けれど、今こうして国境の上でお尻を突き出して笑い合える仲間と、この逞しい体がある。誰かと響き合いながらも、個としての芯を保ち続けること。この「個としての確立」こそが、私が今求めている本当の静寂なのだ。
不揃いな麺と調律の時間
笑い転げたあと、私たちは国境近くで雲南風のカオソイをすすった。 見上げれば、タイの山奥であるはずのこの街には、中国語の看板が溢れている。かつて内戦に敗れ、雲南からミャンマーを経てこの地に辿り着いた国民党軍の末裔たち。そして、国境の向こう側から逃れてきたタイヤイ(シャン)の人々。
ここは、いくつもの「境界」を越えてきた人たちが、ようやく安息を見出した場所なのだ。
私たちが啜ったのは、チェンマイ名物のココナッツミルクのカオソイとは全く違う、透き通った茶色のスープ。白い餅米の塊を削って作られた麺は、驚くほどもっちもちで、削り出されたがゆえの太さの不揃いさがたまらなく魅力的だった。
太いところ、細いところ。 その不揃いな食感は、まるでこの街が辿ってきた凸凹で複雑な歴史そのもののようにも思える。計算された均一さはないけれど、そこには「生きていく」という実直で、温かな力が宿っている。
この不均一な心地よさ。それこそが、今の私の細胞が、そして心が求めていた質感だった。
独り内観の時代へ
帰り道、夕刻の光に照らされたチェンダオの雄壮な山2が、変わらぬ沈黙で迎え入れてくれた。 あの雑踏の中にいたなら、この山の圧をこれほどまでに純粋に受け止めることはできなかっただろう。
今、私は「独り内観の時代」に入ったと感じている。 それは朝、目覚めてすぐの10分間の沈黙や、夜に一日の断片を慈しむ時間だけにとどまらない。
かつて瞑想とは、静かな場所で、特別な姿勢で行うものだと思っていた。けれど今の私は、日常生活のあらゆる瞬間にその扉が開いているのを感じる。 険しい山道でハンドルを握り、路面の感触に全神経を集中させているとき。 不揃いな麺を噛み締め、そのももちもちとした弾力が喉を通っていく感覚を追いかけているとき。 あるいは、仲間の笑い声が風に溶けていくのを、ただ静かに眺めているとき。
それらはすべて、私にとっての瞑想だ。 自分の外側で起きている出来事を、ジャッジすることなく、ただ「今、ここにある質感」として自分自身の軸で受け取ること。その観照者3としての視点を持っている限り、私は日常のどの瞬間においても、深い内観の海に潜っていられる。
本当の静寂は、確かに人混みの中では見つけにくい。 だからこそ、私はあえて今の自分の純度に合わない賑やかさを避けるという選択をした。それは自分の静寂を守るための、大人の嗜みのようなもの。
けれど、ここで一つの矛盾に気づく。 独り内観を語りながら、私は仲間と笑い、共に旅をし、同じ麺を啜っているではないか。
この矛盾の先に、私が見つけた答えがある。 本当の独りとは、物理的に孤立することではない。 それは、誰かと手をつなぎ、響き合いながらも、自分の感覚のハンドルだけは決して誰にも渡さないということだ。
仲間との笑い声の中でも、私は私という個の静寂を保ち、同時に彼らの存在を、自分を補完してくれる豊かな響きとして受け取っている。 独りであるからこそ、他者との純粋な共鳴が可能になる。 自分という楽器が正しく調律されていなければ、誰かと美しいハーモニーを奏でることはできないから。
国境の壁の前で、大きなお尻を突き出して笑い合ったあの瞬間。 私は間違いなく独りであり、同時に、これ以上ないほど深い繋がりの中にいた。 そんな矛盾を抱えたまま、私はこれからも、私だけの「しっくりくる」境界線を辿り続けていくのだと思う。
J.S. バッハ(ヴィキングル・オラフソン編)の『Widerstehe doch der Sünde, BWV 54』
日本のタイトルは、「いざ、罪に抗うべし」
バッハが作曲したアルト(またはカウンターテナー)のためのソロ・カンタータ第54番の冒頭曲ですね。
バロックの端正な響きを、静かな情熱で「観照」するようなピアノの音色。 不揃いな麺を噛み締め、自分のお尻を笑い飛ばした後に残る、あの凛とした「独り」の静寂に、この曲が一番しっくりときました。
ヴィキングル・オラフソンのピアノ演奏は、歌の歌詞(宗教的な教え)を削ぎ落として、純粋な「音の意志」だけを抽出したような響きがします。それが、「言葉以前の感覚」や、自分だけの「境界線」を辿る旅に、驚くほどしっくり馴染む感じがして。
- リス族(Lisu): チベットから雲南省を経てタイ北部へと移動してきた山岳民族。独自の鮮やかな色彩の衣装や、自立心の強い文化を持つ。彼らが山の上で守り続けてきた素朴な暮らしの知恵は、現代の「自然回帰」という言葉を超えた、根源的な力強さに満ちている。 ↩︎
- ワット・ファー・ウィアン・イン(Wat Fah Wiang Inn): タイのウエインヘーン郡北端、ピアールアンに位置する、タイとミャンマーの国境線上に跨って建つ寺院。国境線の画定によって敷地が両国に分断された歴史を持ち、境内にはそれぞれの国の様式の仏塔(チェディ)が共存している。シャン族(タイヤイ族)の人々にとっての重要な聖地でもある。 ↩︎
- 国民党軍(孤軍):1949年の中国内戦に敗れ、雲南省からミャンマーを経てタイ北部に逃れてきた中華民国軍の部隊。タイ政府との協力関係のもと、辺境の国境警備を担いながらこの地に根を下ろした。彼らが持ち込んだ雲南文化は、今もウエインヘーンの食や言葉の中に色濃く息づいている。 ↩︎
- タイヤイ族(シャン族):ミャンマーのシャン州を中心に、タイ北部や中国雲南省などに暮らす、タイ系先住民族。独自の言語と、精緻な装飾が施された寺院建築、そして独特な麺料理などの豊かな食文化を持つ。ウエインヘーン一帯は、国境を越えて逃れてきた人々や、かつてこの地を拠点としたシャン族武装組織の歴史が色濃く残る場所でもある。「国境」という概念に翻弄され続けてきた側面を持ち、信仰心と自立心が非常に強いことで知られる。彼らの実直で温かな精神性は、飾り気のない日々の暮らしの中に今も息づいている。 ↩︎
- ドイ・ルアン・チェンダオ(Doi Luang Chiang Dao):チェンマイ北部チェンダオ郡にそびえる標高2,225mの霊山。2021年には、その極めて稀な生態系と、自然と共生する地域文化が認められ、タイで5番目となるユネスコの生物圏保護区に登録された。石灰岩特有の切り立った岩肌を持ち、天候や光によって刻一刻と表情を変える。その圧倒的な静寂と存在感は、見る者の内面を映し出す鏡のような役割を果たし、深い思索や瞑想を促す場となっている。 ↩︎
- 観照者: 思考や感情に巻き込まれず、一歩引いた場所から「今、ここ」を静かに見つめる意識の状態。自分を分析する「観察」とは異なり、ジャッジ(判断)を介さずに、ただ存在のありようを映し出すこと。 ↩︎