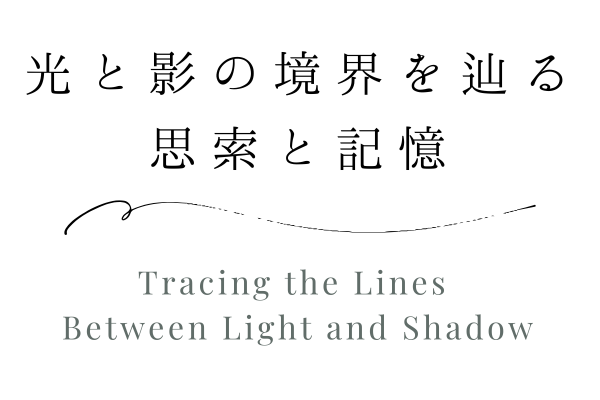カリール・ジブラン「預言者」— 死と苦しみについて考えた新年
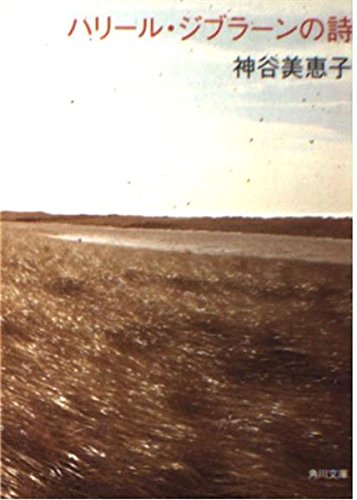
レバノンの詩人、カリール・ジブラン(ハリール・ジブラーン)の『預言者』。
華やかな宗教書でも、難解な哲学書でもなく、人生の途中でふと立ち止まり、静かにページを開きたくなる本だ。
愛、結婚、子ども、友情、善悪、自由、与えること、祈り、そして死……。
人間にとって避けられない普遍的なテーマについて、わたしたちの善性を信じながら語りかけてくれる言葉の集積。
2018年のはじめ、
「これからどう生きていくのか」
そんな問いを抱えながら、新年最初の時間をこの本と共に過ごしていた。
死について ― わたしを慰めてくれた言葉
その中でも、ときどき戻ってきては、何度も反芻してしまう章がある。
それが「死について」。
夫の突然の死から、どうにか現実と折り合いをつけていこうとしていた頃、私はたくさんの「死」に関する本を読んだ。
その中で、この短い詩がどれほど静かな慰めとなってくれたことか。
For what is it to die but to stand naked in the wind and to melt into the sun?
死ぬとは、風のなかに裸で立ち、太陽のなかに溶け込むことではないか?And what is it to cease breathing, but to free the breath from its restless tides, that it may rise and expand and seek God unencumbered?
呼吸の停止とは、休みなく打ち寄せていた呼吸の波から解放され、
何にも妨げられることなく空へ昇り、広がり、神を探しにいけることではないのか?
残された者にとって、死はどうしても「失う痛み」として迫ってくる。
底が抜けるような悲しみと、嘆きにも似た現実。
それでも、ジブランの言葉に触れていると、
「死は終わりではなく、祝福なのかもしれない」
そんな思いが胸の奥で静かに息を吹き返すのだ。
夫はいま、
大いなる源に溶け込み、
全体とひとつになり、
大きな静かな幸福の中にいる——。
そう思えるとき、心はほんのすこし身軽になる。
わたし自身も、余計な荷物を少しずつ降ろしながら、いつか魂がまた全体へと還っていくその日まで、与えられた人生をただ生きていくのだと思うのだ。
宇宙的な視点から見れば、一人の死は巨大な悲劇ではなく、絶え間なく続く生命の循環の中で淡々と営まれる出来事のひとつにすぎないのかもしれない。
わたしたちが「死」と呼んでいるものは、肉体と、そこに強く絡みついている「わたし」という自我がほどけていくことなのだと。
苦しみについて ― わたしたちの内側にある「癒す力」
死の章と並んで、心に残るのが「苦しみについて」の言葉。
(以下、私訳)
Much of your pain is self-chosen.
あなたの苦しみの多くは、自ら選び取ったものIt is the bitter potion by which the physician within you heals your sick self.
それは、あなたの内なる医師が、
病めるあなたを癒そうとして与える苦い薬Therefore trust the physician, and drink his remedy in silence and tranquility.
だから、その医師を信じて
静かに、その薬を受け取りなさいFor his hand, though heavy and hard, is guided by the tender hand of the Unseen…
その手がどれほど厳しくとも、
それは見えざる優しい手に導かれているのだから
苦しみはただ「不運」や「不幸」として降ってくるだけのものではなく、
ときに、私たちの奥底にある癒しの力が選び取るプロセスなのだ——。
それは厳しくも、深い慈しみを前提とした苦しみ。
この言葉を胸に置いてみると、
人生で起こる困難や痛みも、
ほんの少しだけ違う光の中で見えてくる。
アニメーション版『預言者』

本がもちろんおすすめですが、アニメーション版をご存じの方もいるのではないだろうか。
いわゆる子ども向けの作品ではなく、むしろ大人だからこそ沁みる内容。
映像の美しさに導かれながら、
ジブランの言葉が静かに胸の奥へ染み込んでいく作品だ。
見るたびに涙が溢れてしまうのは、
きっと彼の言葉が「悲しみ」ではなく「魂の記憶」に触れてくるからかもしれない。
ただ、アニメではごく一部の詩しか扱われていない。
もしまだ『預言者』に触れたことがなければ、
ぜひ本のページをゆっくり開いてみてほしい。
「生きるとは何か」
「愛するとは何か」
「苦しむとは何か」
そして——「死とは何か」。
答えを押しつけずに、
静かな灯火のような言葉で、
私たちを自分自身へと立ち戻らせてくれる一冊である。