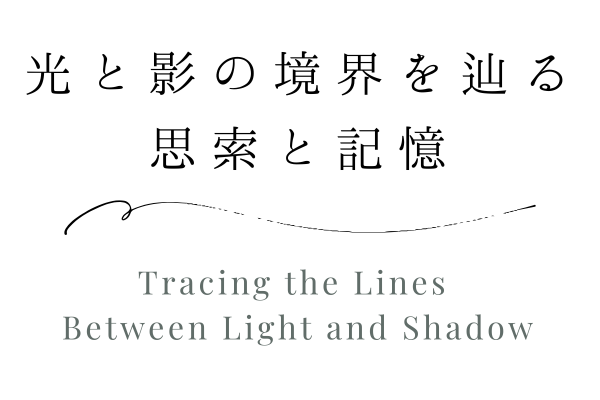〜アニータ・ムアジャーニの講演からPart1−5〜 私が聞き取り、書き留めていた記録 ―
この投稿に関して、まずはなぜこの講演を訳して記録しておこうと思ったのかの理由をPart1-1に「アニータ・ムアジャーニの言葉と、今のわたし」として書きましたので、ご参照いただければと思います。
どこにも属せなかった子ども時代
あの領域で、私が最初に出会った存在のひとりは、父でした。
父は、私がこの体験をする10年前に亡くなっています。
両親はヒンドゥー教徒で、私はヒンドゥー教徒として育ちました。
育ったのは香港ですが、文化的にはほとんど中国で、当時は英国領でした。
両親は私に英語を学ばせたくて、私は英国人学校に通っていました。
そのため、私は幼い頃から英語、広東語、両親のインドの方言という、複数の言語と文化の中で育ちました。
学校では、私はいつも「馴染めない」と感じていました。
人種も文化も違い、他の子どもたちとはどこか違っていたからです。
両親に連れられてインドへ行っても、今度は「西洋的すぎる」と感じ、そこにも自分の居場所はありませんでした。
英国人の子どもたちの中では、肌の色も違い、十分に英国人ではないという理由で、いじめられました。
中国文化にもなじめず、私は生涯を通じて、「自分が本当に属している場所がない」と感じて生きてきました。
父の期待に応えられなかったという思い
成長すると、両親は私にお見合い結婚を勧めました。
私はそれに強く反発しました。
そして、結婚式の3日前、私はその結婚から逃げ出しました。
それは、家族やコミュニティにとって大きな恥となり、私は「わがままな娘」というレッテルを貼られました。
父は、私が十分にインド人らしくない、十分に女性らしくない、伝統的なインド人の妻としてふさわしくない、そう感じていたのだと思います。
父が亡くなったとき、私はずっと、自分は父を失望させ続けてきたという思いを抱えていました。
向こう側には、判断がなかった
私は、父と再会したとき、何かしら判断されるのではないか、あるいは、許しが必要なのではないか、そんなふうに思っていました。
でも、あちら側には、判断は一切ありませんでした。
判断がなければ、許しも必要ありません。
誰かを許すためには、まずその人を「悪者」にしなければならないでしょう。
でも、そこには、善も悪もありませんでした。
身体とともに、剥がれ落ちるもの
私たちが死ぬとき、身体を脱ぎ捨てます。
そして、身体と一緒に、性別、人種、文化、宗教、信念、自我やマインド——そうしたものすべてが、剥がれ落ちていきます。
生涯をかけて幾重にも重ねてきた社会的なフィルターも、身体とともに外れていくのです。
では、何が残るのでしょうか。
残るのは、あなたの純粋なエッセンスです。
それは、あなたの目を通して世界を見ている内なる神、あるいは、神と呼んでもよいもの。
そのエッセンスは、純粋な愛そのものでした。
私たちは皆、そのエッセンスであり、その表現なのです。
父もまた、文化の中で生きていた
あの領域で、私は理解しました。
父は、私を傷つけようなどとは、一度も思っていなかったのです。
私が文化の犠牲者だと感じていたのと同じように、父もまた、文化の中で生きていた人でした。
父が私のためにしていたことは、娘にとって最善だと信じる相手を見つけること。
それが、父なりの、精一杯の愛だったのです。
私たちは互いに、自分が知る限りで、最善を尽くしていました。
そこでは、私から父への判断もなく、父から私への判断もありませんでした。
許すことも、許されることも、何ひとつ必要ありませんでした。
そこにあったのは、ただ、純粋な無条件の愛だけだったのです。
考察メモ〜この章の要点(まとめ)
- 「理解すること」と「許すこと」が、まったく別の次元にあると気づかされたこと
- 私たちが背負っている罪悪感の多くは、文化や役割から生まれているのではないかという問い
- 判断が消えたとき、人と人の関係はどれほど静かにほどけていくのか