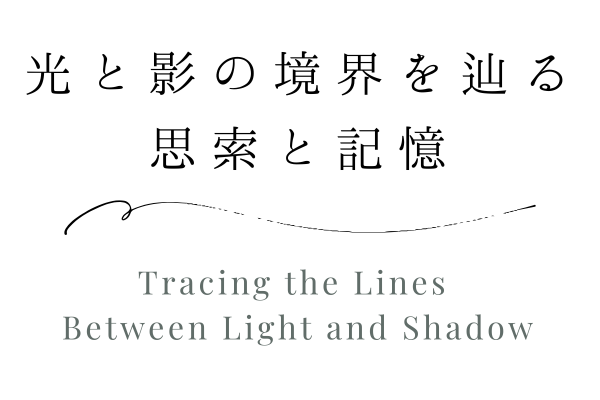タンザニアの真夜中、焚き火の輪の中で
21〜22歳の夜、タンザニアでヒッチハイクをしていたとき、トラックの運転手一家と真夜中の荒野で小さな休憩をとることになった。
焚き火の外へ一歩――闇が「虚無」になる
あの夜、私は小さな焚き火の明かりを背に、暗闇の外へと歩み出した。
火は人の輪をかすかに照らしていたが、その炎はあまりに小さく、ひとたび背を向けると、世界はたちまち光を失った。
闇は単なる「見えない」という状態ではなかった。
それは存在そのものを吸い込み、輪郭を消し去る、圧倒的な虚無だった。
恐怖がすぐに訪れた。野生動物の影を想像し、背後に気配を探りながら、足はすぐに立ちすくんだ。
しかし、その恐怖の深さこそが、やがて新たな視界を開いた。
星のざわめきと、宇宙に呑み込まれる感覚
闇に目が慣れた瞬間、頭上は無数の星々であふれた。
それは「星空を見た」というより、「宇宙の存在に呑み込まれた」と言うべき体験だった。
そして私は、音のないはずの空に、星のざわめきを聴いた。
もちろん星が音を立てるわけではない。
けれど、想像を絶する無数の光が同時に在るという事実そのものが、耳の奥を震わせるように感じられた。
星はただ輝いているのではない。私の存在を問い直すように、冷たくも確かな光で世界を満たしていた。
トーキングドラム:闇を越えて届く鼓動〜トゥツオーラとイーノ
そのとき遠くから、トーキングドラムの音が響いてきた。
地上の鼓動が、天の光と呼応するように続いていた。
人間の声は届かなくても、リズムは闇を超え、星と共鳴する。
あの音はまるで「存在は孤立していない」と告げる声のようだった。
その感覚は、『やし酒のみ』を思い起こさせる。
現実の地面を踏んでいるのに、どこか異界の縁を歩かされているような感覚。焚き火の輪の外に広がる暗闇は、ページの中で出会ったこの世と別の領域の境目と、妙に似ていた。
そして年月が過ぎてから、私はトゥツオーラの『ブッシュ・オブ・ゴースツ』にも出会う。
そこに描かれる、世界の輪郭がふっとずれていく感じが、あの夜の記憶ともう一度つながった。
体験が先にあって、読書が後から追いついてくる・・・そんなふうに、記憶は別の角度から照らし直されたのだと思う。
さらに時を経て、ブライアン・イーノとデヴィッド・バーンのアルバム『My Life in the Bush of Ghosts』が、その記憶を音として呼び覚ました。
なかでも “The Carrier” の、不穏でありながらどこか静謐な響きは、焚き火を背に闇へ足を踏み出した私の心情そのもののようだった。
闇に包まれながらも、星と太鼓に迎え入れられ、人間の小ささと同時に、宇宙とのつながりを強烈に感じていた。
闇は恐怖であり、宇宙の扉だった
あの夜、私は知った。
闇は恐怖であり、同時に宇宙の扉でもあることを。
焚き火が照らし出すのは、人間の世界の小ささにすぎない。
その外側には、星々の永遠の光と、太鼓の響きに満ちた「命の草原」が広がっていた。
火に寄り添えば安全だ。
けれど、闇へ踏み出さなければ、あの星々には決して出会えなかった。
境界の外へ一歩出た瞬間にだけ、見えるものがある。
そしてその一歩は、勇気というより、呼ばれた結果だったのかもしれない。
今になって思う。
暗闇は欠落ではなく、光を立ち上がらせるための背景だった。
恐れは試練ではなく、私がどこにつながっているのかを思い出させる入口だった。
62歳になった今も、あの夜の記憶は鮮烈だ。
星を見上げるたび、私はそこへ引き戻される。
小さな焚き火を背に、闇へ歩み出し、宇宙の深淵に触れた――あの一瞬へ。
そして今の私は、あの夜よりずっと多くを知っているはずなのに、本当に大事なことは、あの闇と星の中で、もう受け取っていたのだと感じることがある。
(この投稿の写真は、素材サイトからダウンロードした南半球の天の川)