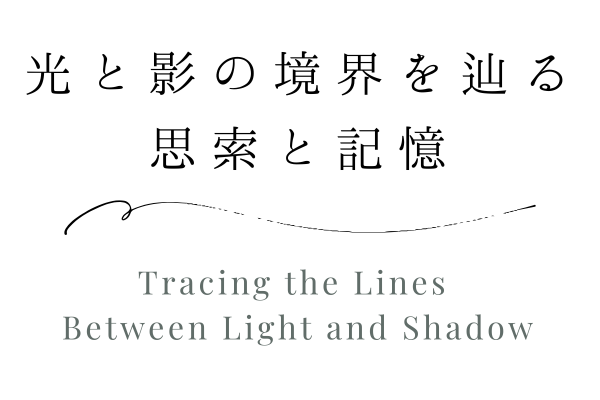記念日というものに、亡夫はどこまでも無頓着な人だった。
日本でのバレンタイン、彼は「日本式」を熱烈に支持していた。大のチョコレート好きの彼にとって、この日は「大義名分を持ってチョコを頬張れる日」という、実利に満ちた記念日だったから。職場でも義理チョコをたくさんもらっていた。あの満足げな顔を思い出すと、尊重していたのは愛よりも「チョコそのもの」だったのではないかと、今でも可笑しくなる。
アメリカでの記憶が薄いのも、今なら納得がいく。ロマンチックな恋愛に限らず、広い意味の愛や好意を表す日で、家族や友人とカードを贈り合う穏やかな日常の風景に、バレンタインが溶け込んでいたからだろう。
そして、タイのバレンタインも同様に幅広くプレゼント交換がされているようだが、男性から女性へ花束(特に赤いバラ)を渡すのがとても一般的らしい。街角に急造された花売り場のバラを見て、彼は一輪、私に差し出した。 「あ、バラ売ってるな。買っていくか」 そんな心の声が透けて見えるような、実になんの気負いもない、無造作な一輪。
当時は「ずいぶん適当に買ってきたよね……」と、その「ついで感」に少しばかり不満を感じたものだった。せっかくのバレンタイン、もう少し吟味して、わざわざ選んでほしかった。
けれど、今、あの頃を振り返って思う。 街角でふとバラが目に留まったその瞬間、彼の頭の中には、真っ先に私の顔が浮かんだのだ。 わざわざ演出しようとしなくても、日常の景色の中に「私」という存在が、反射的に結びついていた。
「ついで」に思い出してもらえること。それは、特別な日にだけ頑張る愛情よりも、ずっと深く根を張った、日常の一部のような愛だったのかもしれない。
あの無造作なバラの赤は、今の私には、当時の不満をすっかり溶かしてしまうほど、温かく、鮮やかに思い出される。
自分のことをふと思い出し、誰かがバラを一輪買ってくれるということが、どれほど尊く、贅沢で、幸せなことか。わざわざ用意された特別な言葉よりも、その「ふと思い出された」という事実の中にこそ、確かな愛が宿っていたと感じている。
バレンタインデーは、今も変わらず巡ってくる。けれど、あの無造作な一輪のバラは、もう二度と手にすることはない。