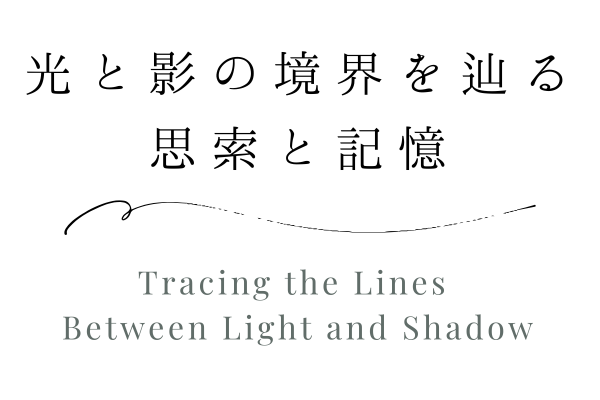一昨年の12月、私はFacebookのタイムライン一つの出会いについて書いた。荒削りだけれど、触れるものすべてを笑顔に変えてしまう魔法のような力を持った、チェンマイの若き(うちの子たちより若いw)ロックバンドのことだ。彼らのことを知って1年半ちょっと。当初はひとりでこっそり楽しんでいたのだが、今や友達も大勢巻き込み、楽しい推活になっている。
彼らの快進撃は止まらない。最近ではライブバーの扉が閉まりきらないほどの熱狂で、私が誘った友人たちもみな今や立派な「沼の住人」だ。真剣な話が続いていたので、今日は最近の私の「推活」事情について、少しゆるりと書いてみたい。
「批評家」を引退させる音楽
以前のFBの投稿にも書いたことだが、私は、音楽を聴くとき、どこか「小姑」のような目を持っている。音楽家の精神性を、腕組みをして探るように聴くのが私のスタイルだ。多分音楽家からしたら、嫌なタイプの鑑賞者なんだろうなあと思う。それが自動的に起きてしまうからめんどくさい。
けれど、今の私の推しバンドのステージを前にすると、そんな理屈は霧散してしまう。彼らがサンタナの熱いリフを刻み始めると、会場の空気が一変。たくさんの可愛い若い女の子のファンたちに混じって、若干いる私のような「熟年チーム」も負けじと音楽を楽しみはじめる。男性客も多い。彼らのレパートリーが古いから、私がかつて熱く来日コンサートに通い、レコードを買い集め、ラジオに耳を傾けていた時期の楽曲と重なるため、一緒に歌える曲もいっぱいある。TOTOやFleetwood Macの曲なんて最初から最後まで一緒に歌える(笑)還暦を過ぎて「細胞まで若返る感じがする」なんて言うのは気恥ずかしいのだが、これは比喩ではなく実感なんだよ。
若い頃、私自身もロックバンドのキーボード奏者として没頭していた時期があったし、ありとあらゆる外タレの来日コンサートに行くのが何よりの楽しみだった当時を思い出し、あの頃の血が騒ぐ。
チェンマイの大らかさと、私のこだわり
ここチェンマイのライブバー事情は、驚くほど大らかだ。基本的に入場は無料。しかも「最低いくら以上の注文を」というようなルールさえ、ほとんど見かけない。極端な話をすれば、カフェのコーヒー一杯分にも満たないような出費で、プロの熱演を何時間も楽しめてしまう。そんな街の懐の深さが、ここには息づいている。
けれど、その大らかさに触れるたび、私の中にある個人的な「こだわり」が静かに頭をもたげる。
私はお酒に弱いのだが、ライブの夜は最初の一杯のマルガリータだけでなく、必ず追加注文をするようにしている。(最初はいつも弱めのマルガリータw)それは、私がこれまで長年、ここチェンマイでのクラシック音楽の現場や音楽家たちの活動を間近で見続けてきたからかもしれない。
文化を育てる側としての責任感
演奏だけで生計を立てることの厳しさ。仕事を掛け持ちし、練習時間を確保するために心身を削る音楽家たちの姿。「音楽家は、演奏することこそが仕事」なのに、その当たり前の権利が守られるためには、聴き手である私たちがその価値を認め、対価を循環させることが不可欠だと思うのだ。
たとえ入場無料の場所であっても、そこには確かに「価値」が存在する。本来ならチケット代として払うべき感謝を、私はドリンク代という形でその場所に置かせてもらいたい。バーの売り上げが増えれば、ミュージシャンへのギャラも増えるであろうことを予想している。これはチップとはまた別のものだ。
それは、私なりの「文化を育てる側としての責任感」。 彼らが音楽を続けていける「場」が、明日もここにあるように。そんな少し不器用な、でも私にとっては譲れない「美学」なのだよ。
ゆるむ、ということの豊かさ
通訳の仕事や日々の思索、真剣な向き合いが続く毎日。だからこそ、こうして音に身を任せて、理屈抜きで笑える時間が必要だと感じる。これは音楽の深淵さを追求することとは違う次元のように感じている。
普段は徹底的に音楽の精神性探る私が、彼らの前ではただの「ロックおねーちゃん」(あ、いやロックばーちゃんかなw)に戻る。音楽の語源は「音を楽しむ」。その原点に立ち返るとき、自分の生命力は確かに再起動しているように感じられるのだよ。
今夜もまた、グラスを片手に、弾けるようなリズムに身を任せてこようと思う。若き才能たちが紡ぐ「自由な音」の守り人の一人でありたいと願いながら。
チェンマイで、一緒にこのバンドの推活(と言ってもライブにいくだけ)したい人!一緒に楽しもう!